 投資哲学を求めて
投資哲学を求めて 法人格と日本的経営、経世済民は繋がっていた?
先日、法人格の仕組みがAIと相性がいいと言う話を聞いて、今まで頭の中でくっついていた「会社=法人」が剥がれた。そもそも会社(とくに株式会社)とは何か改めて考えると、 株主が法人である会社をモノとして所...
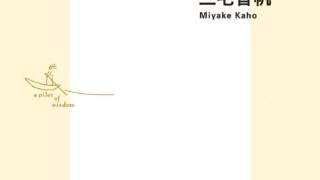 日記と雑談
日記と雑談  日本文化探究の旅
日本文化探究の旅 -320x180.jpg) お薦めの本
お薦めの本 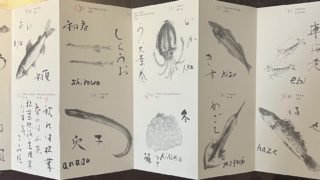 食文化と美食探訪
食文化と美食探訪  日記と雑談
日記と雑談  人工知能をめぐる議論
人工知能をめぐる議論 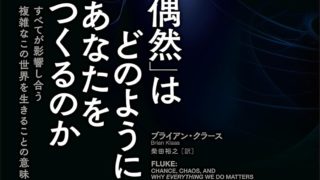 お薦めの本
お薦めの本  食文化と美食探訪
食文化と美食探訪  お薦めの本
お薦めの本  食文化と美食探訪
食文化と美食探訪  お薦めの本
お薦めの本  日記と雑談
日記と雑談 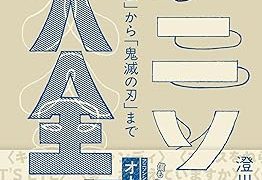 お薦めの本
お薦めの本  日記と雑談
日記と雑談  日記と雑談
日記と雑談