米ソ冷戦終結後の約20年間は、経済成長が最重要視された時代だった。
グローバル化が進展したあの時期がむしろ例外だったのかもしれない。
2010年代半ばからは(特に2014年のロシアのクリミア侵攻あたりから)、
安全保障が注目され始め、地政学の関連書籍の出版が増えてきた。
最近ではすっかり経済よりも安全保障が重要視されるようになり、
地政学は投資家が今まさに学ぶべき分野とひとつと言えるだろう。
私もこれまで何冊か地政学の本を読んできたが、
入門書としてこの上なく読みやすかったのが今日の一冊。
類書に比べて読みやすいのは、情報を詰め込みしすぎず、
分析軸を「海と陸」の地理的条件のみに絞っているから。
- 海洋国家(1章でアメリカ、4章で日本)
- 大陸国家(2章でロシア、3章で中国)
4つの国の地理的な特徴を元にした歴史的動向が紹介される。
- アメリカに立ち向かう対抗連合が存在しないのはなぜか? 他の大国から見て、アメリカとの間に大きな海が広がっているから怖くない。
- 中国やロシアが警戒されるのは、他の大国と陸で繋がっているから。
- ユーラシア大陸に圧倒的な力を持つ覇権国が現れないよう、アメリカはNATOを設立したり、世界の同盟国に基地を置き、世界の勢力均衡を図っている。
- ロシアが攻撃的なのは、西欧諸国と北ヨーロッパ平野でつながっている不安が背景にある。ポーランド(1605)、スウェーデン(1707)、フランス(1812)、ドイツ(1914,1941)に平野から攻め込まれ、滅亡寸前まで追い詰められた過去。
- ロシアのウクライナ侵攻は、海を塞がれる不安とNATOの東方拡大による緩衝地帯の消滅が背景にある。
- かつての中国は遊牧民の侵入に備えて内陸に中心を置いていたが、近年は経済的に豊かな沿岸部の港湾都市が中心。南シナ海への進出は「海の万里の長城」を築こうとしていると考えるとわかりやすい。
- 白村江の戦い(663)以来、日本にとって最も重要な地政学的課題は、大陸勢力との緩衝地帯としての朝鮮半島を守ること。
著者のYouTubeもかなりおもしろいのでぜひ。


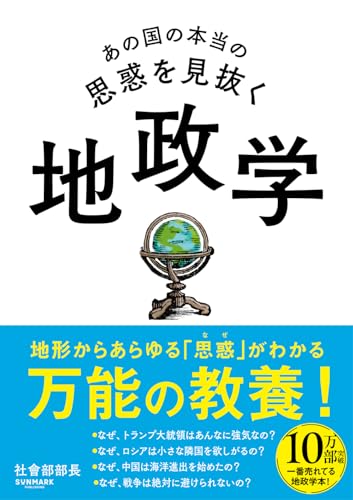


























コメント