 「時」を読み解く
「時」を読み解く 時を読み解く。十数年に渡る探求のまとめ。
「時」というテーマに関心を持ったのはリーマン・ショックの頃。 株価が大きく変動する時は、普段より時間が早く進むように感じた。 以来、時にまつわる気になる記述と出会うたびにメモを残してきた。 それらすべ...
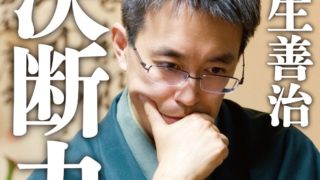 世界を読み解く方法
世界を読み解く方法  お薦めの本
お薦めの本 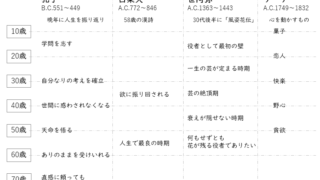 世阿弥「風姿花伝」
世阿弥「風姿花伝」  世界を読み解く方法
世界を読み解く方法 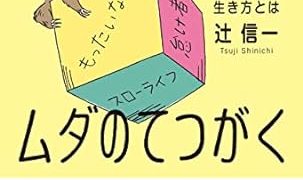 世界を読み解く方法
世界を読み解く方法 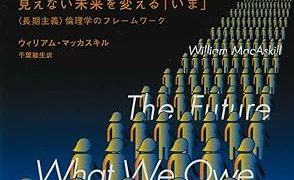 世界を読み解く方法
世界を読み解く方法 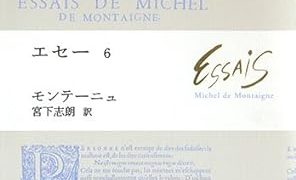 古典に学ぶ人生論
古典に学ぶ人生論 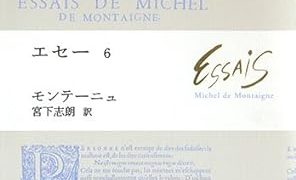 古典に学ぶ人生論
古典に学ぶ人生論 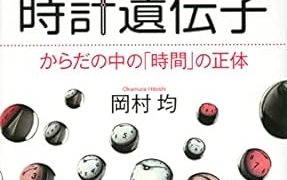 脳と遺伝子の探求
脳と遺伝子の探求 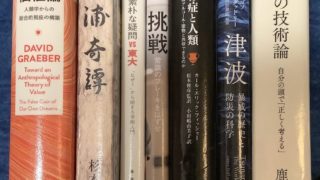 世界を読み解く方法
世界を読み解く方法