ヒマラヤ山脈の隆起と人類の脳容量増大に相関関係が?!
藤井一至「土と生命の46億年史」で出会った驚くべき仮説。
約4000万年前にインド亜大陸がユーラシア大陸と衝突して、
ヒマラヤ山脈とチベット高原が形成された。
そしてヒマラヤの標高が高くなるのを追いかけるように、
サルの脳が巨大化していき、その終着点が私たちヒト。
偶然なのか? もし偶然ではないとするなら…
- ヒマラヤ山脈の発達がアフリカからアジアまで広がるモンスーン気候を大幅に強化した。
- 海洋の湿気を含んだ風がヒマラヤ山脈にぶつかることで大量の雨が降り、この雨が山を削って土砂を大河に運び込む。
- ヒマラヤ由来の大量の造岩鉱物が土へと風化する過程で、炭酸水(大気中の二酸化炭素が溶け込んだもの)が大量に使われる。これにより大気中の二酸化炭素濃度が低下し、地球寒冷化が進行した。
- 地球の寒冷化により氷河期の到来。地球全体の水の多くが極地の氷河に集まったため、乾燥化が引き起こされ、森林は草原に変わった。
- アフリカでは熱帯雨林が分断されることで、サルは森から森へと草原を歩いて移動する必要が生まれた。そこで草食動物を狩るために社会性を身に着けたヒトの脳は巨大化するようになる。
実に興味深い。
ブルーバックスならではの科学用語の連発に苦しめられるが、
頑張って読んでいくと、ビックリする話にたくさん出会える。
普段の生活で「土」に関心を寄せることがないので、
これはぜひとも一読をオススメしたい一冊だ。






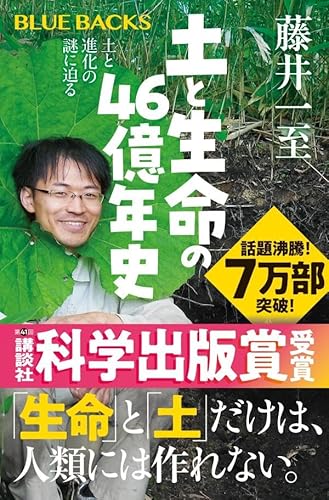










コメント