
邦題が残念な一冊「ぼくがジョブズに教えたこと」。
よくあるジョブズ便乗本ではないのに…。
原題は、
Finding the Next Steve Jobs
How to Find, Keep and Nurture Creative Talent
著者ノーラン・ブッシュネルはゲーム業界の神様。
任天堂ファミコン(1983年発売)より少し前に流行った、
「PONG」という卓球ゲームを作ったアタリ社の創業者だ。
こんな画面のゲームだがファミコン世代の私も見覚えがある。
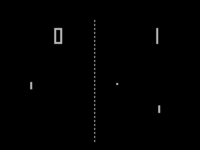
そんなアタリ社に一時期ジョブスが勤めていたことがあり、
アップル創業後に著者の元を訪ねてきて(1980年)、
「創造性あふれる会社にするにはどうすれば?」
という悩みに応じて著者がアイデアを提供したことがあった。
本書の背景をまとめるとざっとこんなところだ。
著者から示される51個に及ぶアイデアは、
経営者や採用担当でなければ関係ないと思いがちだが、
「楽しい人生を送るための知人の選び方」
と読みかえることもできるだろう。
- [6] 多趣味な人を雇え
- [10] クレイジーな人を雇え
知的欲求の高い人間がクリエイティブな情熱を持っている。
彼らの特徴は多趣味であったり、発想がクレイジーだ。
こんな人が社内や知人にいるのといないのとでは大違い。
ちなみにアップルのCM"Think Different"(1997)は、
自分が世界を変えられると信じ込む常識外れの変人が、
本当に世界を変える!というメッセージが込められていた。
- [13] 面接では愛読書を尋ねよ
著者は読書の質問をしたときに身を乗り出してこない人に、
クリエイティブな人は存在しないと指摘している。
私の印象では読書家は情報処理能力が高い人が多く、
決まりきった作業をさっさと片づけてしまって、
余った時間でクリエイティブの種を蒔いている気がする。
- [15] 逸材は案外身近なところに
クリエイティブな人は案外身近に埋もれている。
資格や肩書きで人を判断しているうちは分からないだろう。
- [30] 失敗にこそ賞を
失敗が全くない状態は無理がなく、同時に進歩もない。
いくつかのアイデアを併走させながら失敗は歓迎すべきで、
表彰してしまうくらいの気持ちでなければダメだ。
- [1] 職場を会社の広告塔にしよう
こうした心得を持って会社を経営していれば、
クリエイティブな人が働きたいと感じ、集まってくる。
つまりすべては1番目のアイデアに集約されるのだ。




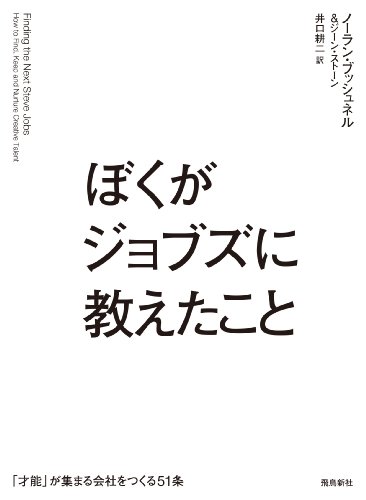


コメント