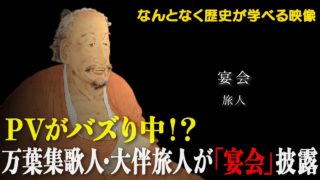 万葉集
万葉集 令和の宴会後、大伴旅人が詠んだ梅歌四首
現在の元号「令和」は、太宰府、大伴旅人の館で開かれた宴会の様子が描かれた、「万葉集」巻五「梅花歌三十二首ならびに序」の序文から取られたことは有名。 梅の季節ということで、その梅の和歌32首に目を通して...
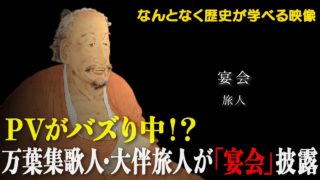 万葉集
万葉集 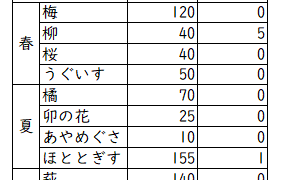 万葉集
万葉集  万葉集
万葉集 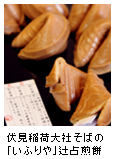 万葉集
万葉集  万葉集
万葉集  万葉集
万葉集  万葉集
万葉集  万葉集
万葉集