 文化で読む日本経済
文化で読む日本経済 武田晴人「日本人の経済観念」
江戸時代から約200年間の経済意識の変遷を描いた、武田晴人「日本人の経済観念」。1999年に出版され、2008年に岩波現代文庫に収録。本棚の整理をしていたら、こんな本あったっけ?と見つけ、ちゃんと読ん...
 文化で読む日本経済
文化で読む日本経済 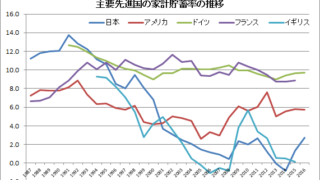 文化で読む日本経済
文化で読む日本経済 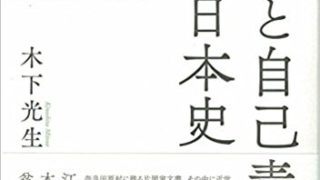 文化で読む日本経済
文化で読む日本経済 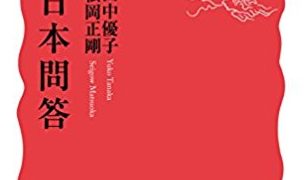 文化で読む日本経済
文化で読む日本経済 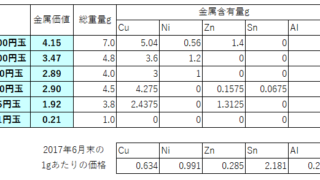 文化で読む日本経済
文化で読む日本経済  文化で読む日本経済
文化で読む日本経済  文化で読む日本経済
文化で読む日本経済  文化で読む日本経済
文化で読む日本経済  文化で読む日本経済
文化で読む日本経済