歴史は時に残酷な事実を突きつけることがある。
木下光生「貧困と自己責任の近世日本史」がその代表例と言え、
「21世紀の日本は、なぜ、かほどまでに生活困窮者の公的救済に冷たい社会となり、異常なまでに「自己責任」を追求する社会となってしまったのか。」P9
という問題意識から、
主に江戸時代の村社会の史料を読み解くことで、歴史的な考察を試みるのだが…。
浮かび上がったのは、過去の日本は助け合いの社会というイメージを覆すものだった。
「各家の自己責任が前提とされていた以上、村の公的救済も臨時的なもので良しとされ、ゆえにそれが「ダダで救う」ような施行という形式をとった場合、受給者は村に迷惑をかけた者としてあつかわれ、屈辱的な日常生活を強いるような厳しい制裁がくだされていったのである。近世日本社会は、自己責任観を強烈に内面化していたがために、公権力も含めて社会全体として、生活困窮者の公的救済は臨時的、限定的なもので構わないとする歴史的特徴を帯びていたといえよう。」P305
ゆえに憲法25条が定めた「健康で文化的な最低限度の生活」の保障は、
日本の歴史文化を読み解くと、あまりに異質で画期的すぎるものであり、
「貧困の公的救済に対する極度の冷たさという、21世紀日本が抱える問題を解決するということは、社会のなかで17世紀以来、300~400年かけて蓄積されてきた歴史的伝統をひっくり返すという、絶望的な営みを意味すると自覚しなければならないのである。」P310
以上が著者による社会全体の貧困救済に対する歴史的な考察だが、
このほか貧困者の志向について興味深かった部分をまとめておくと、
-
貧困者の家計を苦しめていたのは、年貢や借金という非消費支出というよりも、主食費や個人支出といった、自らの消費欲に左右される消費支出部分であり、しかも年間収支がどれほど赤字になろうとも、その消費水準を決して下げようとはしなかった。
-
貧困者は村の公的救済をうけるにあたって、金銭的な負担のない施しより、経済的な負担が多少なりともかかる安価・低利な救済金品の購入・借用をあえて選び、しかもそうした公的救済さえ臨時的なものでかまわないと考えていた。
前者は「年収に見合った生活」という助言が歴史的にそぐわないものであり、
後者も掛け合わせると、私たちの自尊心が貧困解決を難しくしていることが分かる。
最近はSDGs(持続可能な開発目標)という言葉が流行語のようになり、
貧困撲滅といえば海外の話を取り上げる流れができているが、
歴史を踏まえると、国内の問題こそが極めて深刻と感じられる。
しかし現代の感覚は、歴史的に見て正しい状態と考えざるをえず、
おそらく本書の読者が生きているうちに解決できる課題ではないのだろう。



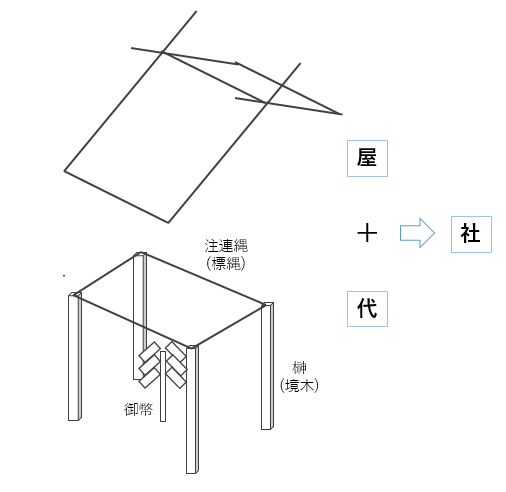

コメント