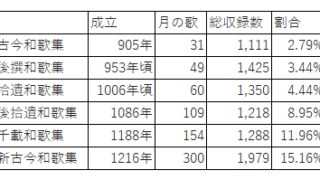 西行「山家集」
西行「山家集」 中世の月食は不吉。でも西行は月が好きだから見たい!
先日の皆既月食は空が雲に覆われていてまるで見えなかった。外に出れば見えるかな?と図書館へ本を返却するついでに出かけてみると、多摩川の堤防の上に人があふれていた。昔の人があの光景を目にしたら、さぞかし驚...
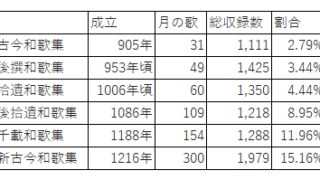 西行「山家集」
西行「山家集」  日本の美意識
日本の美意識  西行「山家集」
西行「山家集」  西行「山家集」
西行「山家集」 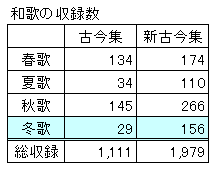 西行「山家集」
西行「山家集」  西行「山家集」
西行「山家集」  日本の美意識
日本の美意識  日本の美意識
日本の美意識  お薦めの本
お薦めの本  西行「山家集」
西行「山家集」