小霜和也「ここらで広告コピーの本当の話をします」。
図書館で調べものの息抜きに、ナナメ読みした一冊。
目に止まった部分を書き留めておくと、
コピーライターとは何をする人なのか?
「商品はいじらずに、言葉を使って商品の価値をあげる人」
広告の役割とは何か?
「モノとヒトとの新しい関係を創ること」
言葉の役割とは何か?
「1つはコミュニケーション。もう1つは思考の補助。」
「言葉が人の行動を決めるのです。 「未来」を考えることができるのも、言葉を持った人間だけです。だからこそコピーという言葉には、企業の未来を決定づけるパワーがあります。」
広告コピーやキャッチコピーというと遠い存在に思いがち。
でも「言語の役割」というところまで広げてみると、
私たちを形づくる言葉のほとんどが広告コピーだ。
たとえば身近なものでは名刺の部署名や肩書き。
ひとりよがりにカタカナでカッコをつけただけで、
どう見られたいのか?という視点が抜けていたりする。
こんな会社には仕事を頼みたくないものだ。
また社訓のようなものも広告コピーだ。
心に響き、覚えやすいものでなければ意味がない。
先日、糸井重里さんがテレビ番組で、
次世代に自分の事務所を託すにあたり、
やさしく、つよく、おもしろく
の順番に大切だと伝えたい、と話していた。
さすがにうまいなぁーと感じるとともに、
ふと思い出したフレーズがある。
"If I wasn’t hard, I wouldn’t be alive. If I couldn’t ever be gentle, I wouldn’t deserve to be alive."(男は強くなければ生きていけない。優しくなければ生きている資格がない。)
---レイモンド・チャンドラー「プレイバック」
こんな言葉も背景にあるのかなと。
人が良き広告コピーに囲まれているかどうかは、
その人自身の教養と連動しているのかもしれない。



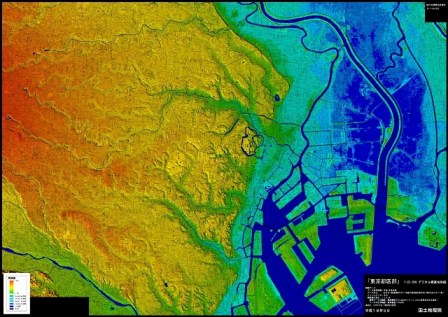

コメント