老舗の語源は「仕似せる」という動詞なのだそうだ。
日本の古典にも次のような例があり、
「かようの万物の品々をよくし似せたらんは、幽玄の物まねは幽玄になり、強きは自ら強かるべし」(風姿花伝)
「譲状にて家督請取、仕にせおかれし商売」(日本永代蔵)
風姿花伝は「まねること」、日本永代蔵は「絶やさず守り継ぐこと」を表す。
あくまで「似せる」ことなのだから、単に同じものを守り継ぐのではなく、
前のものに似せながら、時代に合わせて新しくしてこその老舗なのだ。
たまに老舗の味に首をかしげながら、
「まぁ歴史を食べることに意義があるのだ」
と自分を納得させることもあるが、本来の老舗の形ではないのだ。
(砂糖が貴重だった時代をそのまま、砂糖たっぷりが素晴らしいみたいな…)
そういえば野村進「千年、働いてきました」では老舗製造業の共通項として、
- 同族経営は多いものの、血族に固執せず、企業存続のためなら、よそから優れた人材を取り入れるのを躊躇しないこと。
- 時代の変化にしなやかに対応してきたこと。
- 時代に対応した製品を生み出しつつも、創業以来の家業の部分は、頑固に守り抜いていること。
- それぞれの「分」をわきまえていること。
- 「町人の正義」を実践してきたこと。
上記5つのポイントをあげられていた。
1~3はまさに「仕似せる」経営だなぁと感じたのだった。

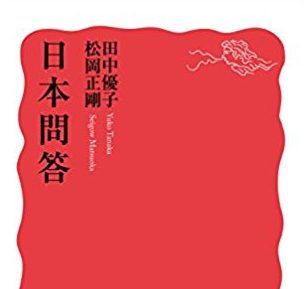
コメント