古今和歌集(905年)と新古今和歌集(1205年)。
この300年で大きく変わったのは冬の美の再発見。
雪の和歌を比べるとその変化が見てとれる。
古今和歌集では紀貫之の雪を花に見立てた歌や
雪降れば 冬ごもりせる 草も木も
春に知られぬ 花ぞ吹きける
冬ごもり 思ひかけぬ 木の間より
花と見るまで 雪ぞ降りける
百人一首にも収録された坂上是則の
夜明けの雪明かりを月光に見立てた歌がある。
朝ぼらけ 有明の月と 見るまでに
吉野の里に 降れる白雪
このように雪そのものの美しさを読んだ歌ではなく、
雪を花や月に見立てた和歌が古今集に詠まれている。
でも新古今和歌集になると、
式子内親王や後鳥羽院が詠ったような
さむしろに 夜はの衣手 さえさえて
初雪白し 岡の辺の松
この頃は 花ももみぢも 枝になし
しばししな消え 松の白雪
松の緑と対比した雪の白さをめでた和歌が現れる。
「雪月花」は古来からの日本の美意識に思えるが、
雪そのものの美を見出すのは平安末期からなのかも。
そして「白」の美しさの発見は、
やがて現れる「余白の美」にもつながるのだろうか。


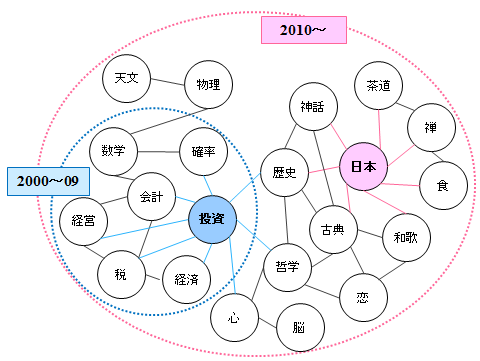
コメント