私たちが様々な社会現象に連続性を見出したがるのはなぜか?
タイトルに惹かれて、パース「連続性の哲学」を読んでみた。
「思考における、感情における、行為における一般化、連続的体系の豊かな拡がりこそが、人生の真の目的である。」P124
これが目をひいた一文なのだけど、私の考えとは真逆だ。
意味、意義、目的、目標といった言葉を人生に押しつけるのが嫌いで、
- そもそも人生に意義や目的はない
- それでも求めてしまうのは現代人の贅沢病にすぎない
生きる意味を遠くに探すことは、なんと息苦しく、愚かなことか。
目の前にあるものが人生のすべて。徒然草に学んだことだ。
- つれづれ(徒然)に込められた人生観(11/12/28)
- 生きてある日は今日ばかり-徒然草の死生観(12/01/06)
連続性と言うと「時」について考える必要があるけど、
特別な瞬間にしか過去・現在・未来を線でつなぐことはできない。
「線」ではなく「点」で時を捉えるのは日本的なのかもしれないが。
もちろん本文中で納得した一節もあった。
知識の進歩を妨げる4つの有害思想としてかかげた(P65-67)、
- 絶対的な断言
- いくつかの事柄は絶対に不可知であると主張すること
- 科学におけるあれこれの要素が根本的かつ究極的であり、他のものから独立であって、それ以上の説明を寄せつけないと主張すること
- あれこれの法則や真理が、最終的で完全な定式化を与えられていると主張すること
イアン・ハッキング「偶然を飼い慣らす」で紹介されたパースは、
偶然の哲学に関係のある人かと思ったのだけど、この本ではイマイチ??
ともあれ老子が愛した水のように、しなやかに様々な考えを取り込みたい。




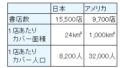
コメント