青色発光ダイオードの開発にノーベル物理学賞。
そうか。ここでも青は人類の憧れだったわけだ。
 絵画の世界では青色顔料はラピスラズリ(瑠璃)。
絵画の世界では青色顔料はラピスラズリ(瑠璃)。
大変高価な鉱物で仏教では「七宝」のひとつとされ、
ヨーロッパでは聖母マリアを描く時に使われていた。
ツタンカーメンのマスクの青もラピスラズリだ。
17世紀にフェルメールが作品にラピスラズリを多用。
「真珠の耳飾りの少女」(1665)が有名だね。
フェルメールの死後、莫大な借金があったのは、
ラピスラズリの購入が原因だったのかも。
自然界から青色を取り出すことは難しく、
化学的に青色が作れるようになったのは18世紀。
 それがプルシアン・ブルー(紺青色)。
それがプルシアン・ブルー(紺青色)。
- 葛飾北斎「富嶽三十六景」(1823~1835)
- ゴッホ「星降る夜 アルル」(1889)
にはこの青が使われている。
つまり青色を自由に使えるようになってから200年。
人類が絵を描き始めたのは、約5万年前なのに。
だからこそ青は私たちにとって憧れの色なのだ。
文学においても憧れの象徴としての青。
- ノヴァーリス「青い花」(1800)
- メーテルリンク「青い鳥」(1908)
といったあたりがすぐに思いつく。
もっと身近な例では青い空、青い海への憧れ。
そして人生でもっとも大切な時期は青春だ。
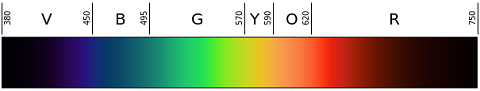
ふと光のスペクトルを見てみると、
波長が短い紫外線の方にいってしまうと有害。
光の安全と危険の間に「青」という色が存在する。
ギリギリのわくわく感が憧れの根底にあったりしてね。

コメント