険しい道のりの先に小さな祠。
そんな神社を訪れた時に地元の方から、
「こういう場所が本当の神社で、観光地化している大きな神社は、仏教伝来後の寺院に対抗して作られたものなんだよ。」
なんてことを教えてもらった。
神と交流するために豪華な社殿は必要なかった。
自然の脅威の中に神が宿ると考えたのだから、
祭るべき大木や巨石があれば十分だったのだ。
その他の仏教の影響を調べとみると、
神事の祝詞は仏事の読経に倣って整えられたようだ。
ちなみに神道が仏教に与えた影響もあり、
祖先を供養する習慣は、もともと仏教には存在せず、
日本に古来からあった習慣と結びついたものだ。
渡来のものに既存のものを組み合わせるのは、
文化のたまり場ゆえの日本特有の方法といえる。
だから本来は何か?なんて読み解くのは意味がない。
でも豪華な社殿よりも自然の中に祠がポツリ…
なんて形の方が神を近くに感じられる気がした。


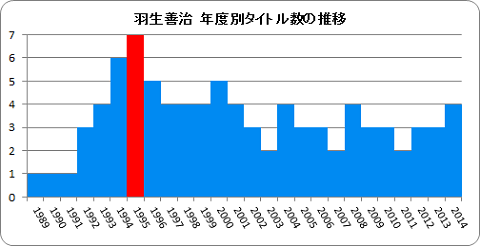
コメント