日本の美意識は「無常→数寄→幽玄→わび・さび」と流れている。
この系譜に時の権力の移り変わりを合わせると見えてくること。
富や権力に取り憑かれた、時の権力者への反逆から生まれたのでは?
満ちては欠ける月、はかなく散る桜を愛し、「無常」を詠った西行。
彼は平清盛とピッタリ同世代で、もともとは武士だった。
貴族化する平家に、世の無常をつきつけたかったのかもしれない。
また「幽玄」といえば、能の大成者、世阿弥。
「秘すれば花なり。秘せずは花なるべからずとなり。」
という「風姿花伝」の名言に代表されるとおり、
あえて隠したり、省いたりすることで、受け手の想像力にまかせる。
そうすることで、すべてが限りあるこの世界に無限の美を演出する…。
この感覚は、豪華絢爛の金閣寺を築いた足利義満への反逆かも。
そして「わび・さび」と言えば、茶道の千利休。
日本平定に飽きたらず朝鮮出兵と権力の拡大を図る豊臣秀吉に対し、
茶室を極限まで小さくし、手が届く範囲の美を突きつけた。
まさに反逆の精神。そして利休は秀吉に切腹を命じられる。。。
ここまで書いてふと思う。
日本がバブル経済に沸いた頃、美意識は動かなかったのかな。
何かないか探してみよう、っと。
※関連記事…幽玄(有限)の中に無限の美を見る(11/06/26)


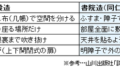
コメント