食べた料理が記憶に残りやすい店とそうでない店がある。
同じように美味しいはずなのに、それはなぜか?
そんな疑問にチャールズ・スペンス「おいしさの錯覚」が科学的に答えていて、
私が繰り返し食べに行く店に当てはまる例が多く、とても興味深い。
著者によれば料理の記憶は失われやすく、
お客の記憶に残りやすくするためのアドバイスとして、
- 一品目に工夫をこらす
- 料理にまつわる物語を話す
- 持ち帰り用のメニューを渡す
- 食事の最中にメニューを提示する
- デザートが全体の評価を左右する
といった方法を掲げている。
一品目に工夫をこらす
著者は人間の記憶の方法を考えれば、一品目の料理が記憶に残りやすいと説く。
「ある経験の詳細を一つ残らず記憶するのは、作業として単純に大変だ。だから脳は〝認知的な近道〟を使おうとする。たとえば、最高の瞬間と最低の事柄や、食事の始まりと終わりを覚えようとする(これを専門用語では「初頭効果と親近効果」と言う)。」
懐石料理では献立の中で最も視覚を刺激する「八寸」が一品目だ。
また次のポイントにもつながるが、旬の食材で季節を表現していることで、
季節と料理が一体の体験となり、より記憶に残りやすいのだろう。
料理にまつわる物語を話す
「大筋のストーリー、あるいは物語の枠組みといったものを提示すれば、食事客はその食体験を構成要素、いわゆる〝チャンク(記憶を容易にするために個別の項目をひとまとまりにグループ化したもの)〟に分解しやすくなる。そして、チャンクになった体験ほど、記憶されやすくなる。」
たしかにここ数年で一番はっきり覚えている料理が、
2016年9月に「菊乃井」で食べた「松茸の土瓶蒸し」。
村田さんが料理の歴史や正しい食べ方などを聞かせてくれたからだろう。
持ち帰り用のメニューを渡す
「必ずしも味の記憶ではなく、むしろ食事全体の思い出と、料理はこんな味だったかな、といった想像が刺激される。この意味では、メニューが詳しければ詳しいほど好ましい。」
これは「SALONE」グループの特徴。
料理の絵または写真とともに食材の説明付きのメニューを食後に渡される。
横浜店のランチは予約が取りにくく、日比谷ミッドタウンにまで進出。
こうした人気の秘密のひとつが持ち帰り用のメニューにあるのかも。
食事の最中にメニューを提示する
「理解するために頭を使って深く考えなければならない出来事(そして料理)こそが、ほんとうに長く記憶に残る。これは心理学では「処理の深さ」と呼ばれる現象で、処理が深ければ深いほど、記憶は長続きする。」
この方法に昨年「Takumi」で出会った。
料理が運ばれてくる前に、その一皿の説明書とともに、
料理に使用した調味料などの小瓶が並べられる。
できあがりを待つ間に香りとともに、どんな一皿か想像して楽しむ。
このことによって記憶が長続きするのだ。
ただ昨年11月に初訪問し、今年2月に再訪したところ、
魚の種類を変えただけでソースは前と同じ、と分かるほど記憶に残っていて、
もう少し間をあけて食べに行った方がいいのかな?と思ってしまった。
デザートが全体の評価を左右する
「食事の記憶をよりよくするための最後の提案は、「終末効果」として知られる現象と関係している。どんな経験においても、記憶というものは最後に起こった物事に大きく左右される。食事も例外ではない。したがって、食事を高評価なもので終えると、楽しい思い出になる。」
麻布十番の中華「老四川 飄香」はデザートが素晴らしい。
多くの中華のランチは、なくてもいいような杏仁豆腐で締められる。
しかし飄香は今の時期なら「いちご大福」が絶品。
都内の中華ランチでNo.1.のデザートはこの店だと思っている。
そのことをお店の方に話したら、良い印象で店を後にしてもらうために、
デザートも手抜きなしがシェフのモットーなのだという。
お昼時に麻布十番にいると、デザートの記憶で飄香に足が向くのだろうか?





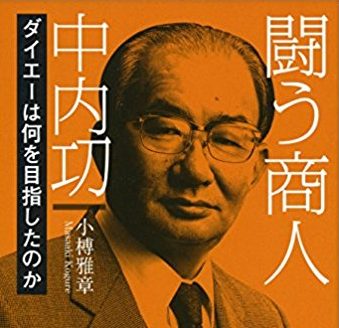
コメント